最近、テレビのニュースでスポーツクライミングの話題があげられることが多くなってきましたね。
でも、スポーツクライミングは何をすれば勝てるのかよくわからないという人、意外と多いのではないでしょうか。
ルールがわからないと、東京オリンピックなどで試合を見ていても楽しくないですよね。
自力で調べるのも、もともと有名なスポーツ以外は難しいと思っている方も多いのではないでしょうか?
それに、専門用語も多いから少し聞いたくらいではわからないですよね。自分も始めてすぐのころ、どうしたら勝てるのかあまりわかっていませんでした。
でも、ご安心ください!この記事では、どうしたら勝てるのか、初心者さんにもわかりやすくご紹介していきます。ぜひ参考になさってくださいね。
実は、勝つ方法は意外と単純!?
え!?そうなの?と思ったあなた。実はスポーツクライミングすべてにおいて勝つのに必要な同じ条件があるんです!
それは、ルートを全て登りきることです!
意外だと思った人が多いと思います。当たり前!と思った人もいると思います。
でも、ルートを全て登りきることがスポーツクライミングにおいて勝つための必要最低条件なんです!
これは、サッカーやバスケにおいてゴールを決めることと同じことといえばわかりやすいと思います。
でも、ルートを登り切れればスポーツクライミング全てで勝てるかといわれると、そうではありません。
サッカーやバスケがゴールの形状や方法が違うように、スポーツクライミングの種目によって勝つ方法が少しずつ異なっています。その違いについて次の章で説明しましょう。
合わせて読みたい

初心者にもすぐわかる!種目別の勝つ方法
ボルダリングで勝つ方法
ボルダリングでは、どれだけ多くのルートを少ない回数で登り切ったのかで勝負します。
ボルダリングの大会やジムのコンペでは、予選、準決勝(ない場合もある)、決勝それぞれに複数のルートが用意されています。
予選で用意された複数の課題を全員で登って、登ることができた(これを完登といいます)課題が多かった選手が準決勝にいきます。
準決勝で完登できたルートの数(これを完登数いいます)が多かった選手が決勝戦に進出して、決勝で最も完登数が多かった選手がその大会で優勝することができます。
予選から準決勝にあがるときは上位20人、準決勝から決勝に上がるときは上位6位以内が進出します。
また、ルートの中にゾーンと呼ばれるホールドがあって、そこを通過したかどうかとクリアするのにかかった回数の合計も順位に反映されます。
リードクライミングで勝つ方法
リードクライミングは、一つのルートの中を6分間でどれだけ高いところまで登れるかを競います。
しかし、大会などの競技では実際に高さは測らず、何個目のホールドまで行けたかで勝敗を決めます。
同じホールドまで行っている場合は、次のホールドに手を出そうとしたかどうかで決めます。
時間切れになったり、反則があった場合はその時点での高度が獲得高度となります。
予選から準決勝にあがるときは上位26名(予選が2グループの時は13名ずつ)、決勝には上位8名が出場できます。
ちなみに、先ほどルートを全て登りきることが勝つための必要最低条件と言いました。
しかし、リードクライミングではルートを完登する選手はほとんどいないので、完登できた時点でほぼ優勝確定となります。
大会によってはルートを完登できる選手がいない時もあります。それほどリードクライミングの大会のルートは難しいということです。
スピードクライミングで勝つ方法
スピードクライミングは、とにかく参加選手の中で一番早くルートを登った選手が勝ちます。
わかりやすいですよね。しかもこれ以外に難しいルールはありません。誰が見ていても、スポーツクライミングのなかで一番ルールがわかりやすいです。
たぶんスポーツクライミングを始める前の自分も、スピードクライミングだけは勝敗がわかると思います。
スピードクライミングの大会ではほかの二つの種目と違って、決勝はトーナメント式になっています。
予選では二回トライすることができます。その二回のうち早かった方のタイムが上から16位以内に入る選手が決勝に進出します。決勝では二人ずつで一緒に登ってタイムを競います。
今から大会に出るために、ルールがわかりやすいスピードクライミングをしよう!と思った皆さん。
残念ながら日本には現在、スピードクライミングができるところが7か所しかないんです(2018年11月時点)。
しかし、まだ完璧に諦める必要はありませんよ!今、スピードクライミングができるところを増やそうというプロジェクトが東京で行われています。
今後スピードクライミングが増えて、あなたの自宅や近所にスピードクライミングの壁ができるかもしれませんね。
複合競技
複合競技では、ボルダリング、リードクライミング、スピードクライミングの3種目の順位それぞれをかけてその合計ポイントで競います。
あれ?順位が下の方がポイントが高くなるけどおかしくない?と思いますよね。
そうですよね。僕も知ったとき若干戸惑いました。複合種目の合計ポイントは低い方が順位が上になるんです!
例えばボルダリング2位、リードクライミング3位、スピードクライミング1位の選手とボルダリング5位、リードクライミング8位、スピードクライミング10位の選手の場合、一人目は6ポイント、2人目が400ポイントとなります。
この場合は一人目の選手の方の順位が上になります。
ボルダリングとリードクライミングにある変わった共通ルールとは?
今まで紹介した方法で、スポーツクライミングの勝敗が決まります。
しかし!特定の条件の場合、ボルダリングとリードクライミングには今まで紹介した以外にほかのスポーツにあまりない順位の決め方があるんです!
それは、カウントバックです!
カウントバックとは?
カウントバックって何?と思った皆さん。大丈夫です。今からわかりやすく説明していきます。
カウントバックとは順位を決めるすべての要素がまったく同じ選手が出たとき、前の結果(決勝→準決勝、準決勝→予選)で順位を決めることです。
例えば決勝で2位が二人出たとき、一人目が4位で2人目が1位の場合、2人目が2位で一人目が3位になります。
これってサッカーでいったら引き分けになったとき、その前の試合の得点数でその試合の勝敗を決めるということになります。変わってますよね。
合わせて読みたい

まとめ
ボルダリングでは登ったルートの数と回数、リードクライミングでは登った高さ、スピードクライミングではルートを登るのにかかった時間で勝負します。
この記事で知った情報を参考に、スポーツクライミングの大会の動画をもう一度見てみるのはいかがでしょうか。
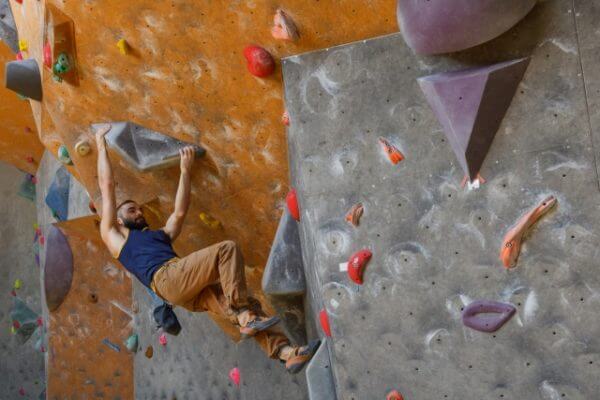


コメント